
長月の由来は、「夜長月(よながつき)」の略であるとする説が最も有力だそうです。 まさに「秋の夜長」がはじまりますね。他に、「稲刈月(いねかりづき)」が「ねかづき」となり「ながつき」となったという説、「稲熟月(いねあがりづき)」が略されたものという説もあります。 いにしえより主食をご飯にしている私たちの生活が「稲」という文字に垣間見ることができます。
秋の二十四節気 処暑の圓應寺の行事
・禾乃登(こくものすなわちみのる)9月2日頃
いよいよ稲が実り、穂を垂らす頃。「禾」は稲穂が実ったところを表した象形文字。
秋の二十四節気 白露の圓應寺の行事

白露は朝は少し冷えるようになり、草花に朝露がつくという意味です。
二百十日と同じ厄日であり、台風シーズンを意味する二百二十日があります。
十五夜と言われる、中秋の名月があります。
ちなみに十五夜の翌日の十六夜(いざよい)というお月見をする風習もあります。
段々と秋の旬の食べ物が増えてきて、サンマや梨と言った秋の味覚が旬を迎え食欲の秋の到来ともいえます。
また重陽の節句という五節句があります。
・草露白(くさのつゆしろし)9月7日頃
草に降りた露が白く光って見える頃。朝夕の涼しさが際立ってきます。
9月 9日 火 重陽の節句
重陽は、五節句の一つで、9月9日のこと。旧暦では菊が咲く季節であり、 菊を用いて不老長寿を願うことから菊の節句とも呼ばれます。 陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽数の極である9が重なる日であることから「重陽」と呼ばれ、不老長寿や繁栄を願う行事をしてきました。
また、庶民の間では「お九日(くんち)」と呼ばれて親しまれ、秋の収穫祭と合わせて祝うようにもなりました。有名な「長崎くんち」「唐津くんち」はその名残で、新暦の10月に開催されています。
9月 10日 水 14:00 読誦行
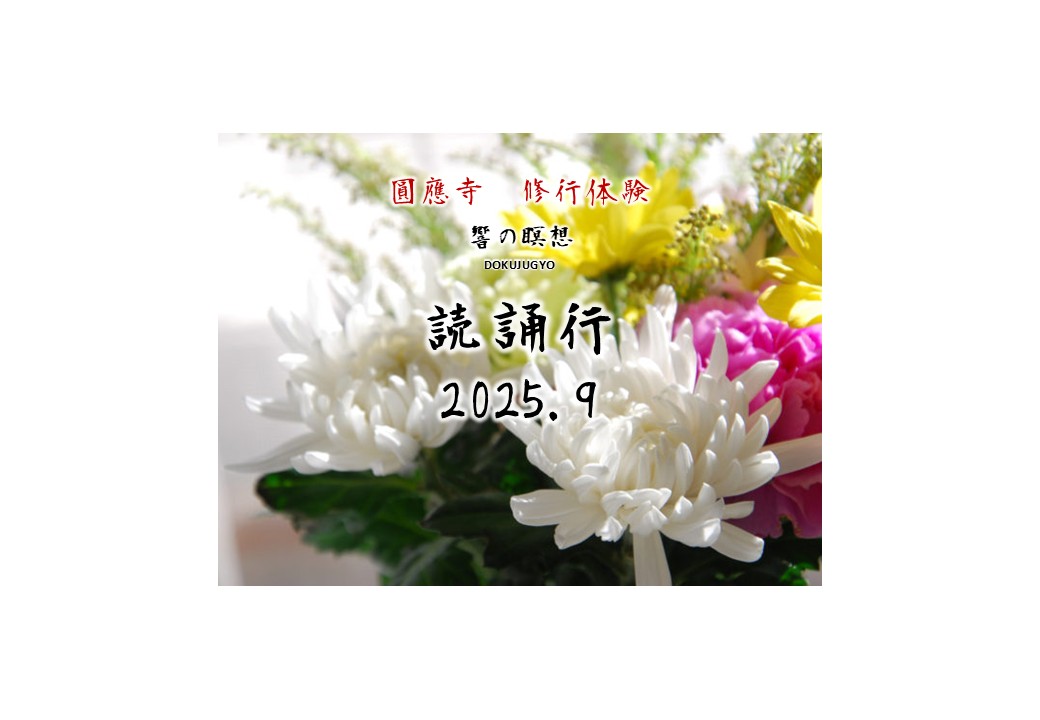
・鶺鴒鳴(せきれいなく)9月12日頃
せきれいが鳴き始める頃。せきれいは日本神話にも登場し、別名は「恋教え鳥」。
9月14日 日 18:30 観察行(瞑想会)『其光如光』
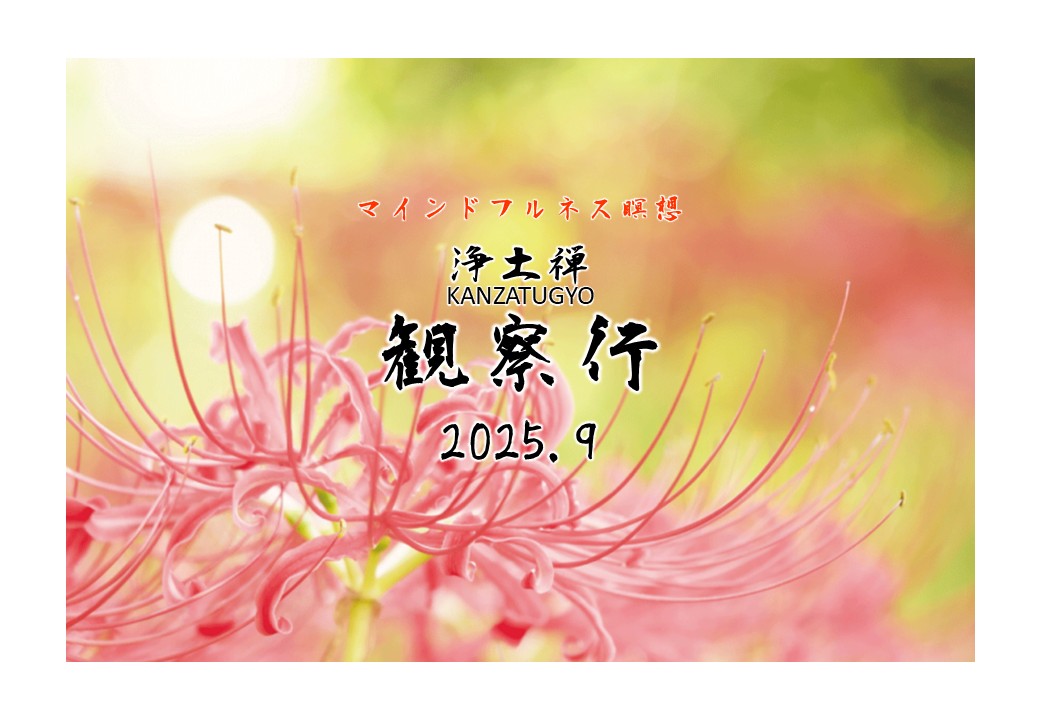
9月 15日 月 9:30 ~淨の瞑想(meditation)~ ココロを磨く、整える 作務

・玄鳥去(つばめさる)9月17日頃
燕が子育てを終え、南へ帰っていく頃。来春までしばしのお別れです。
秋の二十四節気 秋分の圓應寺の行事

秋分は春分と同じく太陽が真東から昇り真西に沈む日で、秋彼岸があります。
秋分になると秋も深まってきている時期となり、松茸などの旬の食べ物が見られるようになります。
秋分の日もお彼岸の中日となり、秋のお彼岸があります。
9月21日 日 11:00 弁財天月法要
9月22日 月 11:00 圓應寺 秋彼岸会法要
・雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)9月23日頃
雷が鳴らなくなる頃。春分に始まり夏の間鳴り響いた雷も、鳴りをひそめます。
2025年は9月23日 秋分の日

9月24日 水 15:30 ~武の瞑想(meditation)~ 拳禅一如

9月26日 金 11:00 今津正覚寺 彼岸会法要
・蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)9月28日頃
虫たちが土にもぐり、入口の戸をふさぐ頃。冬ごもりの支度をする時期です。
9月28日 日 18:00 写経写仏会



