葉の落ちる月「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」というようになりました。現代の感覚では葉が生い茂る様子を思い浮かべますが、旧暦では7月から秋となるため、秋真っ盛りだったのです。
夏の二十四節気 大暑の圓應寺の行事

大暑は一年でも最も暑さが厳しい時期を意味します。
圓應寺では、7月13日から8月15日までの期間、地獄極楽絵図を本堂に掛けまして、ご参詣の皆さまに拝観できるようにいたしております。
この地獄極楽絵図には、臨終を迎えて、七日七日に裁かれ、遅くとも四十九日にはどの世界に生まれ変わるかの六道輪廻の様子や地獄、極楽の世界が描かれています。

・大雨時行(たいうときどきふる)8月2日頃
ときどき大雨が降る頃。むくむくと湧き上がる入道雲が夕立になり、乾いた大地を潤します。
8月 2日 水 14:00 ~武の瞑想(meditation)~ 拳禅一如
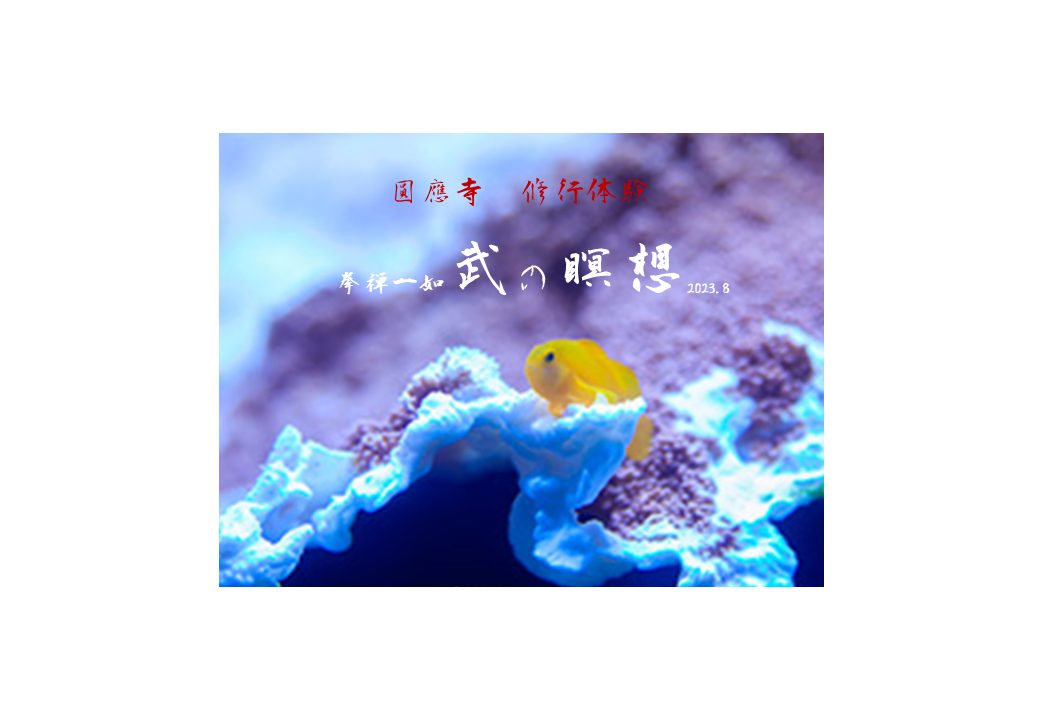
8月 4日 日 18:30 ~動の瞑想(meditation)~圓應寺 礼拝行 『施餓鬼』

8月 5日 月 14:00~圓應寺寺子屋 【お香教室】
8月6日 火 13:00 ~響の瞑想(meditation)~圓應寺 読誦行

秋の二十四節気 立秋の圓應寺の行事

立秋からは暦の上では秋となりますが、一年で最も暑い時期です。
暦の上で秋を迎えても立秋の時期は夏の暑さはピークを迎え、秋を実感しにくいかもしれません。しかし、徐々に空は高くなり、うろこ雲やいわし雲など秋特有の空模様が見られます。
立秋を過ぎると暦の上では秋を迎えますが、暑い日はまだまだ続きます。暑中見舞いや残暑見舞いは、送った方に季節を感じさせることがでる、大切なコミュニケーションツールの1つです。今まで暑中見舞いや残暑見舞いを出したことがなかった方も、今年の夏は季節のあいさつ状を出してはいかがでしょうか。古くから日本に伝わる良き風習を後世にも残していきましょう。
残暑見舞い
残暑見舞いは、「立秋」から「白露」までの時期に送りましょう。また「残暑」とは、「立秋」から「秋分」までの期間を指します。残暑見舞いを送る時期は、暦の上では秋です。そのため、暑中見舞いとは使用する時候のあいさつが異なります。立秋を過ぎてもまだ暑さが残っているからといって、夏の時候のあいさつ文を使用しないよう注意してください。
立秋は「朝と夕方が涼しくなり、秋の気配が現れる」という意味を持っています。立秋の日を境に、暑中見舞いは残暑見舞いへ切り替わり、時候のあいさつも「暦の上では秋ですが」や「立秋を前にまだ暑い日が続きますが」など、立秋を意識したあいさつが増えます。
立秋の間にはお盆がやってきます。一般的には(関西を中心に)お盆は8月13日~15,16日を意味します。
お盆は元々は7月15日を中心として行われる先祖の霊を供養する「盂蘭盆会(うらぼんえ)」を起源として、7月に行われます。
13日に迎え火を焚いて、先祖の霊をお迎えし、15日に送り火で霊をお送りします。
・涼風至(すずかぜいたる)8月7日頃
涼しい風が吹き始める頃。まだ暑いからこそ、ふとした瞬間に涼を感じることができます。
8月 9日 金 11:00~ 弁財天月法要
8月 10日 土 盂蘭盆棚経開始(~15日 木)

8月 11日 山の日
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日。
・寒蝉鳴(ひぐらしなく)8月12日頃
カナカナと甲高くひぐらしが鳴き始める頃。日暮れに響く虫の声は、一服の清涼剤。
8月 ①13日 火 18時 ②14日 水 11時 ③14日 水 17時 ④15日 木 18時 合同棚経
圓應寺本堂にて厳修致します。ご希望の方はご一報ください。(当日ご参詣の方はお位牌をお持ちいただき、受付で回向帖をご記入ください。)
8月15日 仲秋 十五夜
立秋となり、暦の上では文字通り「秋」です。そこから八月のことを仲秋といい、15日を十五夜といいます。
8月15日 終戦記念日
8月15日 木 9:30 ~淨の瞑想(meditation)~ ココロを磨く、整える 作務

・蒙霧升降(ふかききりまとう)8月17日頃
深い霧がまとわりつくように立ち込める頃。秋の「霧」に対して、春は「霞」と呼びます。
8月17日 土 11:00 今津正覚寺 施餓鬼法要

秋の二十四節気 処暑の圓應寺の行事

二十四節気の処暑は暑さが収ってくるという意味を持つのですが、中々近年では暑さが残っています。台風のシーズンが到来し、雑節の二百十日(にひゃくとおか)が来ます。
厄日ともされる二百十日は立春から数えて210日目を言い、必ず暴風雨があるとされ、農家の方にとっては台風シーズンを知らせる日です。
・綿柎開(わたのはなしべひらく)8月23日頃
綿を包むガクが開き始める頃。綿の実がはじけ白いふわふわが顔をのぞかせた様子。
8月24日 土 10:00 地蔵盆
境内のお地蔵様をおまつりし、子どもたちの健やかな成長を願い、圓應寺では特に水子のみたまのお盆として8月24日の地蔵菩薩の縁日に行われます。
8月24日 土 13:00 照福院殿遠忌 「光姫忌」2024

圓應寺をお建てになり、菩提寺とされた福岡藩祖黒田官兵衛如水公の正室である照福院殿光姫さまについての歴伝録です。

8月25日 日 18:30 写経写仏会

・天地始粛(てんちはじめてさむし)8月28日頃
天地の暑さがようやくおさまり始める頃。「粛」は縮む、しずまるという意味です。
8月28日 水 14:00 ~武の瞑想(meditation)~ 拳禅一如

圓應寺副住職三木英信がご案内致しました。


